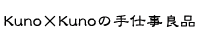 |
#019 [照屋佳信さんのやちむん]沖縄県恩納村 2007.08.24 |

左が「もやい工藝」のスタッフが壺屋やちむん通りで偶然見つけ、
照屋さんがつくったものと知らずに買ってきた、
三彩点打ちの湯飲み。
右は私が所蔵する、金城次郎さん作の湯飲み。
1960年代の仕事だ。
同じ三彩点打ちの技法が施されているが、
照屋さんの物とまったく雰囲気が異なるのがわかるはず やちむん通りでの出合い
平成5(1993)年、私は沖縄の焼き物のつくり手、山田真萬さんと那覇市の壺屋を回った。手仕事日本展に出品する沖縄のやちむん(焼き物)を探していたのだ。当時の私が関わっていた、やちむんは山田真萬さんの物だけだった。壷屋のやちむん通りを歩けば、通り沿いに並ぶ販売店で山田真萬さんの物以外にも沖縄らしい、やちむんにたくさん出合えるだろうと目論んだのだった。
しかし、意外に心をとらえる物は少なかったが、ある店で細長い角型の傘立てを見つけた。それは「切立甕(きったちがめ)」と呼ばれる。木製の型枠で形を整えつつ、陶土をあててつくられた物だ。沖縄伝統のジーシーガーミ(厨子甕=お骨入れ)の本体部をつくるのと同じ方法で、傘立ての寸法に合わせてつくったのであろう。 この傘立てには呉須(ごす)と飴の釉薬を交互に組み合わせた「幾何格子紋(きかごうしもん)」という模様が描かれていた。その物に強く魅力を感じて、店主につくり手を聞くと、照屋佳信(てるやかしん)さんの物だとわかった。 その名前が頭に残り、周辺の人に照屋さんについて尋ねたら、沖縄本島北部、山原(やんばる)で焼いている人で1年に1回、窯出しをする程度でたいして仕事をしていない人という話だった。
その数年後、「もやい工藝」のスタッフが数年後に壺屋やちむん通りを歩いていた時、沖縄の伝統的な技法、三彩点打ちの湯飲みに出合う。この技法は金城次郎さんが得意にしたものだったが、雰囲気が次郎さんのつくるものと違いながらも、素晴らしい湯飲みで、そのつくり手が照屋さんだとわかり、私は矢も盾も居られず照屋さんを探ることにした。
その頃になると、読谷村の北窯とも関わっていたので、北窯の窯元に照屋さんについて聞いたら、渋々、教えてくれた。さらに、そこのお弟子さんたちに聞くと「自分たちは照屋さんに憧れています。久野さんは、とっくに照屋さんのことを知っていると思ったから言わなかったけれど、どうして照屋さんの所へ行かないのかなと思っていました。ただ、なかなか難しい人で、たまに遊びに行くこともできないんです」という話だった。 |
野人の風貌に惹かれる
私は何が難しいのかわからないが、きっとおもしろい人なのだろうと思った。早速「もやい工藝」のスタッフが私より先に照屋さんの窯に行き、工房に残って在庫していたものを寄せ集めて2箱くらいに入れて送ってきた。開けてみると、驚いた。金城次郎さんの1960年頃の仕事ぶりに通じるような、かといって金城次郎さんとは異質に感じる物が出てきたのだ。エネルギッシュで、沖縄の風土性をその物から率直に感じた。
それまではやちむんから感じるというよりも、やちむんをつくっている人から感じていて、物より人から沖縄らしさみたいなものを感じて、その人のつくっていたものを見ていた。照屋さんのやちむんはつくり手本人に会う前に物から沖縄の良さ、凄さを感じさせてくれた。これは照屋さんの窯にぜひとも行かなくてはいけないなと考え、その後間もなく私は北窯の松田共司君に連れて行ってもらった。あいにく照屋さんは不在だったが、お弟子さんが3人いた。そのお弟子さんの顔が非常にしっかりしていた。内地(日本)の陶芸に志をもって生きていこうという若者らしく、沖縄に来て焼き物をやりたいから、その窯に入っているという印象だった。沖縄の各窯元にはそういう人がずいぶん弟子入りしているが、照屋さんの窯は他のお弟子さんを超えた意識を持っているようだったので、「ほう、これはおもしろいな」と思い、照屋さんがいなかったのは残念だが、また来ればいいなと窯を後にして坂道を降りて行った。
翌日、また再訪すると照屋さんが窯にいて、お弟子さんたちから私の訪問のことを聞いていて、訪問の理由も知っていたので、いきなり話が始まった。沖縄土着の焼き物をやっている人は、昔はずんぐりむっくりした体型の人が多いけれど、照屋さんはやせぎすで、見るからに骨っぽい。眼光も鋭い感じがするが、話していると優しい人柄であることがわかる。色が黒くて、ちょっと野人的な雰囲気ももち、何か惹かれるものがあった。話をしていて粗野な部分もあることに気づき、話が長くなると面倒くさがる人だなあと感じた。しかし、人間性は今までの焼き物のつくり手と違うところがあった。ものづくりをする人は物を売らないといけないという商人気質が根本的にあるんだけど、照屋さんは珍しくそういう体質とは違う、素朴そのもので生きている。好きだからやっていて、自由奔放性に生きてきているように感じた。3人もお弟子さんがいるのに、仕事場の中はいたって静寂で、私が彼らから話を聞くと、照屋さんがお弟子さんを求めているのではなくて、逆にお弟子さんたちの方が照屋さんのそばにいて働かせてほしいという感じだった。その若者たちが学識のある連中であることに、私はおもしろみを覚えたのだ。 |

窯で作業する照屋佳信さん(撮影/副島秀雄) |

窯の中の照屋さん(撮影/大部優美) |
沖縄らしい焼き物のつくり手
照屋さんはかつて壷屋のもっとも伝統的な窯である、小橋川永昌(こはしがわえいしょう)さんの仁王窯で勉強をしていたという。最初は小橋川さんの運転手として雇われたが、それほど忙しくなく、仕事場をぶらぶらして職人さんやお弟子さんに話しかけていた。そのうち、そんなに暇ならばちょっと仕事をしてみないかと、土づくりをさせてもらったりしているうちに仕事がおもしろくなってきた。これは自分の肌に合うのではないかと思い、この仕事をやろうと正式にお弟子さんに入れてもらったのだと言う。弟子上がりして、今の恩納村に自分の窯を構えるまでの、私にとって興味があるストーリーを自ら語る人ではないし、また詳しく聞こうと思わせないような雰囲気をもつ人だったので控えた。
恩納村の照屋窯は読谷村から車ですぐ行けるため、読谷の窯の人たちと常に情報が行き交い、お弟子さんたちの間でも私のことはほとんど知られていた。照屋さんはそんなことにまったく興味がないから、私がどこの誰かと気に留めることもなく、ただ話が合うから私が訪問するのを非常に楽しみだと言ってくれた。
その時、彼の製作に関して気がついたことは、製品はどれもかなり分厚く、ロクロの技術は際立って上手だとは思わなかった。しかし、沖縄の粗く赤い土を厚ぼったく挽くところは、金城次郎さんにも通じるところがあって、その厚みを気にせずにつくっていく。沖縄の土がもつ味を自然体として取りこんでいるのだ。この人が持っている感覚というか、体が沖縄らしい、やちむんのつくり手そのものであると私は感じ捉え、さらに惚れてしまった。
つくった物はどうしているのですか?と聞くと、仁王窯のお弟子さん時代からつき合っている業者が4〜5人壺屋にいて、その人たちが自分たちの物を買っていってくれると言う。業者たちは売れるものしか持っていかないから、売れ残った物がこんなにあると見せてくれた。
お弟子さんたちは働きや手伝いで来ているのでなく、照屋さん個人のつくりに魅力を感じ、経済的には厳しい条件下で、それでも働きたいという人たちだという。自分は家族を養うだけでいいので、それで精一杯。それ以上大きなことも考えていないと、きわめて平凡な生き方を貫いている。製品の値段はかなり安いが(もともと沖縄のやちむんは安いが、読谷の物よりさらに安い感じ)、それでも彼からしたら高い、こんなに高い物を買ってもらっていいのかなと思いながらつくっていると照屋さん。別に恰好つけているわけでなくて、本当にそう思っているような人だった。 |

照屋佳信さんの登り窯(撮影/指出有子) |
この人は汚されたくない
照屋さんの焼き物は、まず自分で使ってみたくなってしまうのが第一の印象である。そして、私はこの人は汚されなくないなと思った。私は優れたつくり手に会うと、その良さを知らしめるために、ついその人の名前を一般に公開し紹介してしまう。私が民藝に関わりだして、その時ですでに20年近く経っているが、今までもずっと大胆につくり手の名を公表してきた。そのことが自分の店にはマイナスな部分もずいぶんある。つくり手の名前と、そのつくり手の何が良いか教えてしまうため、ただ単に良い物を探している人にとって、こんなにうまい話はない。だから、日本民藝館展に出品させて名前を明らかにすると、民藝館展を観に来た、東京や地方の民藝店の人たちがどこで誰がつくっているかわかるものだから、取引したいつくり手に電話を入れたり、手紙を出したり、菓子折りを届けたりして気を引いて、そのつくり手の物を仕入れるようになる。私が製作に関わっても横取りされるようなこともしばしばある。
また、せっかく良い物をつくるようにアドバイスしても、いつの間にかその物が他の店に並んでいるということもある。つくり手はたいてい貪欲だから、誰かの恩恵があったと思っても3〜5年すると都合よく忘れてしまって、自分がつくったものになってしまいがちである。そういう割に合わないこともあったが、あえて私はつくり手を知らせることを辞めなかった。 しかし、照屋さんだけは窯も小さいし、この人の良さを物の良さだけで語って欲しくない。沖縄らしい風土性から伝わった造形力をこの人は持っているから、広く知れ渡ってもらいたくないなと感じた。それで照屋さんのことは余計、一般には公表せずに、自分の店だけで主に販売していた。ところが店に置くと、眼識力のあるお客さんが何人もいるから、今までとちょっと違う物があるなと気づき、照屋さんの物だけが欲しいという人が出てきたのだ。しかし、年にせいぜい2回の窯出ししかしないから、生産量が少ない。さらに昔からの付き合いのある店があるため、その人たちをのけるわけにもいかない。ただ沖縄の伝統的な窯というのは注文生産。注文を受けた物をつくっていく。そのため、注文数が多ければまず、そっちが優先されるから、「もやい工藝」も大量に注文書を出した。さらに窯出しにはスタッフが出向いてまでつくりの優れた物、焼きの調子が良い物を最初に選品する。つまりうちにとって良い物が店にいっぱい来たのである。
そういうやりとりを何年か続けていた時、私の出身校、武蔵野美術大学の後輩のつてで、焼き物をやりたいという20歳代中頃の女性、武田裕美子君が訪ねてきた。彼女は武蔵野美術大学の陶芸科を出て、陶芸教室に勤務していたが、自分の目指す焼き物のスタイルとは違和感があったので、地方に行き、伝統的な仕事を続けている窯場に弟子入りしたいと、どこか良いところを私に紹介して欲しいと頼って来たのだ。照屋さんという人がいると教えると、もともと彼女は沖縄に行ってみたかったと言う。給料ももらえないし、自分で生活しないといけないよと付け加えると、「覚悟しています。今まで貯めたお金を全部もっていきます」と言う。そのかわり3年間の蓄えしかないから、3年間限定の弟子入りと約束してお世話になりますと。
照屋さんに交渉すると、久野さんの推薦する人だったら当然受け入れるし、ちょうどうちの窯も一人二人と抜けたところなので(経済的にもたないから抜けざるを得ない)いいよと。私たちにとっては武田君が行ってくれると、もやい工藝でアルバイトをさせていたこともあり、こちらから仕入れに行かなくても、もやい工藝の内容をよく把握している彼女が、出来上がった物を送ってくれるというメリットもあった。それである程度、彼女に託したのだった。
よく気がつき働く子で、能力も高く照屋さんもすっかり気に入ってしまった。また彼女は窯元で働くにはちょうどいい体型だった。小柄できびきびしている。沖縄の窯はもともと北窯のように、内地と同じような窯ではなくて、背が低くてかなりかがまないと作業がしずらい。そういう意味では、昔の沖縄の人らしい、ずんぐりむっくりの人が都合が良い。というわけで、照屋さんとの付き合いはさらに深まっていったのである。 |

泡盛を入れる酒器「カラカラ」。器本体の中にあらかじめ陶土で小さな玉を入れて、酒が空になるとカラカラと鳴る。いわば口付きのとっくり。大きな物も、小さな物もあり、沖縄特有の白化粧土が美しい。注ぎ口の付け根に緑釉が掛かっているが、これは俗に青地釉(せいじゆ)、沖縄では「オオグスヤー」と呼ぶ。沖縄の土は粗いため、焼いて注ぎ口を付けた接着部分が切れやすくなる。それを防ぐために釉薬を掛けた上からさらに釉薬を掛けるのだ。それがまたシンプルでありながら表情を見せてくれる。左側は照屋さんが得意とする三彩点打ちといって、オオグスヤーと飴釉を道具に含ませてぶつけた模様。
薩摩、龍門司焼の影響が伝わる |

まず、泥しょうの錆土を生地に掛けて、それが乾く前に指で瞬時のうちにかき落とす。それから鉄分の強い釉薬を薄く掛けて焼く。右側の按瓶(共手土瓶)は強い酸化炎で焼いたので、きれいな赤い色が出ている。左側の湯飲みは、釉薬がたっぷり残っていて、こちらはやや還元炎がかかっていて焼きが程よい状態で黒い色になっている。これは私が大好きな物のひとつ。
指描きというのは非常に個性的な技法だが、
嫌みを感じさせないところに、この物の良さがあると思う |

対瓶(ついびん)。上側がとっくりで、下側がご飯茶碗を逆にしたような独特なかたち。2つ対にしてお墓の前や神棚の前にお供えする信仰の道具だ。掻き(かき)落としという模様を施しているのだが、こういったものは得てして嫌みな物になるのだが、照屋さんのこの技法を用いると、逆に趣きがある物となる。沖縄のどこの窯場でも対瓶をつくる人は多いけれども、普通は下の部分と上の部分を別々につくって接合する。ところが照屋さんはそのつくりかたを知らずに、最近私が教えた。照屋さんは一本挽きで挽いてきた。そのため、かたちがすっきりしていないが、今でもむしろ素朴で趣きのあるものになっている。掻き落としという模様はけっこう嫌らしい技法で、これだけ激しいコバルトや緑と飴を組み合わせると、普通は首をかしげるような物になりがちだ。ところが照屋さんがそれをやると、なぜか勢いのある活き活きとしたものに変わる。
これが照屋さんの良い個性なのだろう。 |
※焼成(原料を高熱で焼いて性質に変化を生じさせること)の状態によって炎も変化し、それによって焼き物も変化する。低火度の場合は酸化炎焼成となり、高火度の場合は還元炎と酸化炎との両方がある。酸化炎は十分に酸素が供給されている焼きかた。焼成時間は長く、たいてい色が鮮やかに出る。還元炎は酸素が十分に供給されていない状態の焼成。窯内の温度が一定の高温に達したら窯口を閉じて焼成する。 |
|
風土が生む魅力
照屋さんはこちら側から新たな形の物をつくって欲しいという要望を受け入れる体質ではない。可能なのは、模様や技法、大きさを指定する程度なのだ。なぜかというと、彼自身がそういう仕事ぶりなのである。誰かの意見を聞いて、このかたちをつくろうというのではなくて、自分のスタイルを決めたら、そのスタイルから逃げず、固執する人なのだ。そのなかで、おもしろい技法があれば、アドバイスを受けてやってみたいという人なのである。それゆえに彼の得意とする点打ち、緑と飴釉、あるいはコバルトと飴釉、さらに緑の釉薬を筆に含ませて曲面にバンバンとぶつける、照屋さんらしい粗野でいて人を惹きつけるような焼き上がりの美しいものができるのかもしれない。
そういった物の他に、彼は型の物を一生懸命つくっていた。仁王窯で小橋川さんがジーシーガーミや、型でつくる角皿などを修行してつくっていたものだから、彼は石膏枠や木枠でそうした物をつくれるし、得意としていた。それがまた照屋さんの魅力だ。とくに彼がつくるジーシーガーミは小ぶりだが、私が最初に出合った切立の長甕と同じスタイルで、とにかく魅力がある物だった。これはつくっているという物よりも窯の構造、使っている土質、白化粧土などが一体化して生まれる魅力なのだ。
照屋さんの粗野な部分のおもしろさ、照屋さんからにじみ出る技法、体で持っているもの以上に、沖縄の風土が助けてくれているのだ。照屋さんが用いる胎土(生地)はかなり赤味の強いもので、北窯の使うものよりさらに紫色がかっていて、酸化鉄が非常に強い土だ。その上に使う化粧土は名護市の方へ自分で掘りに行って持ってきているもの。この化粧土がとても美しい。そういったものを沖縄の昔ながらの急勾配の窯で焼くと、じっくり空気を送って酸化炎で焼いたとしても、無酸素状態になって還元がかかる(強く焼かれない)ところがある。そうして出来上がる焼き物は一段と私を惹き付けるものがあるのだ。
だが、そういったものが頻繁に出てくるということは、完全製品となるものが半分も(商品として)取れないことが多いということ。1回の窯出しで3割しか取れないこともある。しかし、彼はいくら労力を無駄にしても無頓着なのだ。出来上がった物が良くないと思うと、外に捨てるがごとく窯場の広場に積み上げてしまう。しかし、そのなかに魅力のあるものがすいぶんあるものだから、窯出しに行った時には選り分けて持ち帰ったりするのだった。 |

真ん中に点を打ってお花を表した、沖縄の伝統的な唐草模様。
化粧土をして、染め付けをして、釉薬を掛けている。
焼きは還元がかかって蒸れてしまった。
おそらく窯の中の湿気が非常に高くて、
焼いても焼いても焼き不足だったため、
それでも焼き続けたら、ちりちりになってしまったという仕上がり。
こういう物は登り窯からしかできてくるところにおもしろさがある
|

これは両方とも私の愛用の7寸皿。
沖縄の典型的な深めの皿、
中央が平坦で縁の方にかけてそらせているから使いやすい。
何を載せても合う。左の皿は緑と飴の釉薬を点で打っている。
右の皿は飴釉で唐草模様をあしらっている。
とても化粧土がきれいで、気持ちのいい皿だ |

これも私の愛用の楕円皿。
カレー皿にしたりパン皿にしたり、いろいろな用途に使っている。
型枠に入れて叩いてつくるのも照屋さんの仕事。
これに点を打って、照屋さんの窯で焼くと、
このように赴きのある物ができる |

飴の釉薬で唐草をあしらった、ご飯茶碗。
沖縄ではマカイと呼ぶ。3年間私はずっとこのマカイでご飯を食べている |
均一でない、温もりのある手仕事
照屋さんは一人で陶土づくりから釉薬づくりまでやるものだから、窯を炊ける回数が限られてしまう。約束通り3年後に武田君も辞めてこっちに戻ってきたため、良い助手がいないこともあり、照屋さん自身もつくりの方向が少し弱くなった。そんな時、不幸が起こって、自動車で自損事故を起こし、利き腕の右手が利かなくなってしまった(昨年のこと)。当分はロクロの作業ができず、型の仕事をするしかない。右手で型を押せないので、左手で頑張って、模様を掘ったり、技法を凝らしたりするが、どうしても生産量が落ちてしまい、現在は1年に1回窯出しをすればいいくらいの状況である。だが、内面はどうかはわからないが、彼はそんなことを気にもしない生き方をしているものだから、型の物で魅力のある物がこれからは出来上がってくるのかなと期待したい。
照屋さんのつくる物は、焼き上がりを見てみると、土が暴れているように見える。きれいに焼けない。たとえば若い人たちに受けている出雲の出西窯のように焼き上がりが均一ではない。ところが昔の出西窯は均一にできずに、登り窯の作用で黒や白、コバルトの焼き上がりが変化して、その変化とやや粗いつくりに魅力があった。しかし、今の社会はどうも均一性を求める傾向が強く、デザイン化された物の方に興味がある人が増えてきている。時代の流れだから、やがて変わるだろうが、これも今のこの状態でははっきりいって本来的な見方でいうと、あまりおもしろいものではない。人間の手の温もりみたいなものがあまり感じられないのだ。照屋さんのつくる物は人間の温かさを感じる。若い人に敬遠されるのかなあと思ったら、案外、そういった物に興味を持つ人が増えてきているようであり、知られていけば案外、主流になるのではないかと思うし、そうならなければならない。
下の写真のジーシーガーミーを例に挙げよう。白い化粧土がちりちり(焼けて縮収)になっている。焼く時に、収縮の過程で土がきちんと締まっていないと、こういうふうになるが、逆にそれがまたひとつの独特な魅力を醸し出すし、同じ皿でも焼き上がりの調子によっては、たとえば酸化炎が強いと赤っぽく発色し、還元炎が強いとネズミ色やグリーンがかったりするのだ。 また、下の「いっちん」といって白い化粧土をスポイトで幾何学模様を描いた2枚の皿を見てほしい。片方は赤くなって、もう片方はややモスグリーンの色になっている。これは還元炎で焼かれたのと、酸化炎で焼かれたものとの顕著な違い。両方とも魅力がある。すなわち、照屋さんのつくる物が焼き上がってくると非常に楽しいのは、何か心を打つものが生まれてくるということなのだ。こういうつくり手は日本国内、とくに本土ではほとんどいなくなってしまった。つくるのが上手な人はいても、ここまで自然に、焼き物としての魅力をつくり出せる人は皆無と言ってもいいだろう。以前は小鹿田焼きの坂本茂木さんがいたが、彼自身が窯から手を引かされている現在、唯一のつくり手は照屋さんだけかなと私は思っている。
また、これは言い過ぎかもしれないが、民藝運動の中で柳宗悦が選んできた物と共通する、美しさが表出したものが照屋さんのやちむんの中に見える。もしかすると、沖縄という土壌、風土が照屋さんのようなつくり手を育みやすい地域なのかもしれない。だから、今はそのような状態ではなくても、流れがまた変わるかもしれない。きっと照屋さんのような均一でない物を生みだす、つくり手が出現する余地がまだまだ沖縄にはあるのではないかなと思うのだ。 それゆえ決して、私たちは諦めてはいけない。諦めずに沖縄へ通い、沖縄の若いつくり手たちを勇気づけ、さらに何が良いかということを常にコンタクトしながら、そういう優れたつくり手が自然に出てくるのを待ち、出てきたら助力して、良いつくり手として育成していくことを心がけていきたい。
(語り手/久野恵一、聞き手・撮影/久野康宏) |

これは化粧土をスポイトに入れて「いっちん」という模様を描いた物。
左側は幾何学模様になっていて、右側は唐草をあしらった皿だが、双方とも同じ釉薬を用いている。
透明な白化粧をした上に、透明な釉薬をかけると、酸化炎の窯の中でいぶされて、無酸素状態になってしまうと、左側のようにモスグリーンの調子になる。右の皿のように、空気をたくさん送りこんでよく焼けると赤味を増す。
重ねて焼くため、重ねた中央部分は無酸素状態になり、少しグリーンになっているのがおもしろい |

照屋さんのつくったジーシーガーミ。
表側に亡くなった方の名号を墨で書く。
本来はこれにお骨を入れて、大きなお墓に入れて30年間安置していた。
30年経つとお墓から取り出して、骨をわずかな量にして小さな骨壺に入れ替えて、墓の裏側にある本墓に安置する。
ジーシーガーミは壊してしまうのがしきたりだったのだ。
今、上手にジーシーガーミを焼ける人は照屋さんの他には、私の知る限りは上江洲茂生(うえずしげお)さんだけだ |

ジーシーガーミの裏側には蓮の花が描かれる。
天上の浄土を表している伝統的なスタイル。
昔からジーシーガーミにはこの模様が
貼付け模様として施されてきた |
※かつては沖縄では二度の葬儀、埋葬と洗骨がおこなわれていた。洗骨とは埋葬した遺体が朽ちるのを待ってから、数年後に取り出して、骨を洗い清めること。洗骨された骨は木製やシージーガーミに移し替えて、再び墓に戻す。現代では火葬することが多いため、洗骨の習慣はほぼ消失しつつある |